江戸期刺繍
関東一円を中心に、全国無料で出張買取いたします。
関東の方はすぐにお伺い致します。

東京美術倶楽部(桃李会 集芳会 桃椀会)所属
確かな鑑定力と豊富な販売ルートで
大切なお品物を少しでも高く買い取ります
出張・宅配・WEB
買取対応エリア
買取り1週間以内
キャンセル
東京美術倶楽部(桃李会 集芳会 桃椀会)所属
民芸品とは骨董の中でも広義に渡り限定のしにくい分野でもあります。
民芸(民藝)の定義としてまず第一に 思いつくのは民芸運動(民藝運動)の父、柳宗悦の提唱した・実用性・無銘性・複数性・廉価性・地方性・分業性・伝統性・他力性が挙げられます。生活の中から生まれるその地域に根づいた無名の工人による日常雑器 や日用品にこそ「用の美」があるとした芸術的価値観を唱えました。それによりそれまで注目されることのなかった日本各地の焼き物・染織・漆器・木竹工、さらには木喰の仏像や大津絵などが民衆美術工芸の美として脚光を浴びることになります。
民芸運動(民藝運動)は柳宗悦の他、濱田庄司や河井寛次郎、バーナード・リーチらとともに活動を拡大していきます。
柳宗悦の大きな功績のひとつに朝鮮・李朝美術の再発見があります。当時の朝鮮古陶磁器研究の第一人者であり蒐集家でもあった浅川伯教の紹介により朝鮮古陶磁器に魅了された柳は1924年(大正13年)ソウルに「朝鮮民族美術館」を設立し、朝鮮半島の日常雑器などを展示し、朝鮮雑器の「用の美」を評価しました。そして李朝民藝の立役者にもう一人、青山二郎の存在も欠かすことができません。青山二郎は美術評論家としてだけではなく、骨董蒐集家として有名でした。資産家の息子として生まれた青山二郎は中学生の頃より骨董を買い求めており、その卓越した選美眼は26歳の若さで実業家・横河民輔の蒐集した中国古陶磁器の図録作成を委託されるほどでした。
柳宗悦の提唱した民芸運動(民藝運動)に影響を受け、一時は共に夢を共有していく仲間となるのですが、「柳の提唱する高麗茶碗などはもともと茶の湯において桃山時代から評価され、それは特権階級のものだった。自在鉤も庄屋・地主しか持っていないものである。そういったものは無名の工人により作られたとはいえそれは果たして廉価性といえるのか」「作意を持たない一般の工人の作風に美を見出し、作意をもって近づけることはもはや民藝ではない」などの民芸運動(民藝運動)のもつ最大の矛盾点から離脱します。民芸運動(民藝運動)は事実、北大路魯山人に強烈に批判されており、民芸(民藝)の定義の曖昧さを物語ってもいます。
青山二郎も北大路魯山人も、そして青山二郎に師事した白洲正子も民芸(民藝)が日常雑器に価値を見出す初心を忘れ、民藝を称する河井寛次郎や浜田庄司の作品を美術品並みの値段で取引していることに大きな矛盾を感じたのでしょう。
この点はいまだに終着点が見えていないのですが、それは偏に民芸(民藝)の思想が柳宗悦の美意識に頼りすぎており、そのことの限界が見えているからではないでしょうか。
ただ、柳宗悦が提唱した価値観自体は否定されるものではなく、彼自身が日本中を旅し見つけた日用品に美の感性を持ち込んだことは物に対する我々の見方そのものを問い直すよい指標と言えるでしょう。
一方で工芸品というものもしばしば民芸品として紹介されることがあります。民芸品(民藝品)と工芸品の差は非常に曖昧ですが、伝統工芸品は経済産業大臣指定伝統工芸品というものや各地方自治体が認定するものもあり 伝統的技術や技法の継承、また工人が重要無形文化財・人間国宝に指定されていることもあります。
いずれにせよ各地の風土から生まれた手工業製品という大枠で両者を捉えることができます。
また民芸運動(民藝運動)と同じころ長野県上田を起点とした農民美術運動という活動が始まりました。提唱者は版画家・山形鼎(やまがたかなえ)で、山間部の農民のものづくりを通し農民の増収・特産物の創造・農村改革を促す工業振興運動です。
松本民芸は今でも有名ですが、この運動は日本各地に広がりをみせ、現在物産展などで民芸品が売られるようになった根底にあるのは農民美術運動だと考えられています。
北海道八雲町でも同様に徳川義親が農民美術運動を進めアイヌ工芸と結びつき、今では北海道土産の定番、木彫りの熊が生まれました。
初期の農民美術は木片人形などが多く作られておりましたが、農民美術運動の木彫講習がきっかけで20歳より独学で浮世絵版画を学び竹久夢二に憧れ、郷土・秋田の自然や風景を一貫して描き続けた版画家・勝平得之(かつひらとくし)のような高い芸術性が評価された版画家も生み出す源流となったことは見逃せません。
柳宗悦は農民美術に対し日本の伝統工芸を顧みていないと批判的でしたが、今ではともに美術工芸品、骨董品としての価値を見出されています。
民芸品は生活骨董とも言えるジャンルですので気楽に蒐集できる身近な骨董と言えます。
1960年代から1970代にかけ民芸ブームという社会現象が起きました。高度経済成長期に手作りの持つ温かみに癒され民芸品を手にされた人は少なくありません。しかし民芸品は興味のある方とない方はっきりと分かれるジャンルで、一般の方にはありふれていて使い古された日常雑器や黒ずんだ土産物にしか見えず価値のあるものに見えません。使い古された日用品、一般の方にとって、それははっきりいってゴミと見えます。したがって民芸品は骨董の中で最もゴミとして処分されることが多い分野なのです。
ご自宅で発見された古い木工の皿やお盆、木彫りの熊、古い布や古道具・古民具、お客様が価値を見出せなかった民芸品に価値を見出し評価できるかは買取り業者次第です。民芸品という比較的お手軽な骨董なため様々なリサイクル業者や買取り業者がいますが、中にはその価値がわからず「不当に安い金額で買い取る業者」も少なくありません。
また最近主流となりつつあるメルカリなどのフリマアプリやネットオークションをご利用させる方も多いと思います。気軽に出品でき一見高く売れる気がします。鑑賞用陶磁器など他の骨董品に 比べ民芸品は贋作も少なく、その点においては安心して出品できるかもしれません。
ですが個人で出品するフリマアプリやネットオークションは、まずその民芸品の価値を知らない と適切な値段の設定が難しいです。
フリマアプリは安く欲しい人から値下げ交渉を求められる場合もあり適正な価格を知っておかないと値下げが正しいのかどうか判断が難しいかもしれません。またフリマアプリですと送料を負担しないとほぼ買い手がつかず、さらに売上の1割を手数料が必要となります。手間に対して割に合わないという声をよく耳にします。 ネットオークションも同様に、正当な価格と価値の知識がある方ならお薦めですが、そうでない場合、適切な額で落札されたのかどうか確信することがなかなか困難だと言わざるを得ません。
杉並区を中心に35年、関東一円及び全国で買取り・査定をしてきた経験に基づく「鑑定力」が 弊社の強みです。
特に民芸品は丹波布・科布・芭蕉布・藍染・こぎん刺しなどの刺し子など染織 品も多く、呂芸の持つ最大の強み「古布」がいかんなく発揮できる分野でもあります。
また民芸に対し造詣の深いスタッフが鑑定し、初めてのお客様にもご満足とご安心いただける、寄り添った査定と買取りをさせていただいております。
さらに創業35年で培った販売経路も豊富で、BtoB、BtoC、eコマースとお預りしたお品によって 使い分けることにより高額での買取りを可能としました。
そして迅速に出張査定・買取りへお伺いいたします。民芸品の中には仙台箪笥や松本民芸家具 囲炉裏の自在鉤など重量がありご持参が難しいものがあります。
お伺いの際は懇切丁寧に説明させていただき、押し買いなどすることはございません。お気軽にご相談下さい。
呂芸ではLINEなどでまずは簡易査定のみのご依頼も喜んでお待ちしておりますので是非お問い 合わせくださいませ。
お客様の大切な民芸品をお売りの際は、民芸品高額買取の自信がある呂芸にお任せくださいませ。
見つけた布や骨董品は、洗濯や磨く等せずにそのままにしてください。
基本的には綺麗な状態の方が骨董品の買取価格は高くなりますが、知識もなく磨く事は得策ではありません。
古い状態の物は弱いものが多く、逆に傷がつき価値が下がる可能性があります。
まずは拝見させていただき、価値のあるものでしたら買取させていただきます。
まずは、WEB査定にてお写真をお送りください。
お品物にもよりますが、買取できる場合もございます。
ただ、保存状態のよいお品物に比べると査定額は低下してしまいます。
ただし、価値が完全に無くなってしまうわけではございませんので、まずは一度ご相談下さい。
ただし、破損状況などによっては買取できかねない場合もございます。
お品によっては1点でも出張買取いたします。
まずは、お電話またはWEB査定より品物の詳細を教えてください。
ご不安があるようでしたら、WEB査定にて一度品物のお写真をお送りください。
出張料・査定料は無料です。
買取りにいたらなかった場合でも、費用などは一切いただきません。
その場で買取金額にご納得いただきましたら、即金にて買取させていただきます。
ご納得いただけなければ無理に買取りすることはありませんのでご安心してご利用ください。
いずれか1つご用意ください
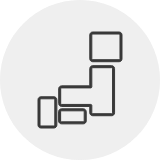
日本全国無料で
出張査定・買取行います。
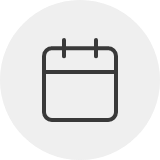
土日も対応可能。
日程調整してお伺い致します。

お値段にご納得頂ければ
その場で現金買取致します。
関東一円を中心に、全国無料で出張買取いたします。
関東の方はすぐにお伺い致します。