江戸期刺繍
関東一円を中心に、全国無料で出張買取いたします。
関東の方はすぐにお伺い致します。

東京美術倶楽部(桃李会 集芳会 桃椀会)所属
確かな鑑定力と豊富な販売ルートで
大切なお品物を少しでも高く買い取ります
出張・宅配・WEB
買取対応エリア
買取り1週間以内
キャンセル
東京美術倶楽部(桃李会 集芳会 桃椀会)所属
能面の高価買取なら創業40年の呂芸にお任せください。
店主自身が「喜多流」に所属していた時期があり、「喜多能楽堂」で能を舞った経験もあり、能面、能衣装、和楽器に造詣があります。また、店主が能面に対する情熱を持ち続けており、能に対する研究を個人的に続けております。
呂芸は東京美術倶楽部の交換会に所属している古美術商であるため、リサイクルショップと違って高価な能面、能衣装の価値を見極めることができます。
また、創業40年の実績があるため、多くの顧客、業者と精通しており、国内・国外のオークションでの販売実績もあります。そのため、販売ルートも非常に多く、高価買取が可能となっております。ご自宅に眠っている価値の分からない能面、能衣装などがございましたら、お気軽にご相談ください。
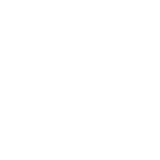
若女
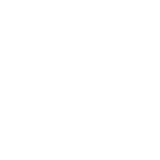
小面
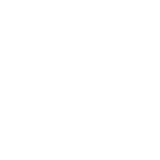
増女
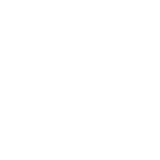
翁
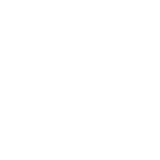
鷲鼻悪尉
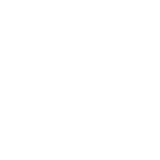
大癋見
能面が良好な状態に保たれていることは非常に重要です。傷、汚れ、損傷などがないことが望ましいです。
能面を保存する際には、直射日光や湿気を避け、適切な保管方法を用いることが重要です。
高額な査定が期待できる能面は、共箱が入っている可能性が高いです。鑑定書や証明書、共箱があれば、買取価格が高くなる可能性があります。
能面、能衣装を高く売るためには、起源を証明できる文書や箱書きがあると有利です。
信頼性のあるギャラリーやオークションハウスで認証された作品は、信頼性が高いとされ、高値で売却しやすくなります。
能面、能衣装の価値を正確に判断するには専門家の意見が不可欠です。
売却される前に専門家に相談し、可能であれば鑑定を受けることがお勧めです。
能面、能衣装を売却する際には、適切な販売先を選択することが大切です。古美術商、オークション、リサイクルショップ、ヤフオク、メルカリなど、異なる方法があります。作品の特性に合わせて最適な販売先を選びましょう。
複数の買取店や専門家から見積もりを取ることで、最も高い価格で買取してもらえる可能性を高めます。
偏に能面や能装束といってもその種類の多さには、能にご興味のない方にとって見分けることが最も困難な分野と言えるでしょう。
能面は時代性・作家性・素材・コンディション・需要と様々な要素でその価値が著しく異なります。最近では海外での人気も高いことから工芸品としての一面もあり廉価版のような形で販売されるものもございます。
そして能装束には各時代の意匠を見極める目と知識が必要不可欠であり骨董品のみならず古布や着物に対する造詣の深さが求められます。
能面や能装束のご売却は能が日本の伝統芸能という面から、その特殊性と特別性を十分に理解した買取業者選びが必要不可欠と言えるでしょう。
能などの日本伝統芸能は古布との関わりが深い文化のひとつです。最小限に要約された動きの中、能面と能装束の織りなす幽玄の美は世界にも類を見ない独特の世界観でさえあります。
能の起源は信仰との繋がりが深く、神仏に奉納するため社寺の境内や拝殿などで演じられておりました。
勧進の名のもと、野外に設置された舞台で行われるようになり、室町時代には観阿弥や世阿弥の出現により人々に鑑賞される舞台芸能として確立します。
江戸時代になると能は徳川幕府や武家の式楽に定められ格式を高めることとなります。
能装束は室町時代の日明貿易もあり、明から舶載した染織品を用いられるようになります。能装束のひとつに「唐織」がございますが、これは元々中国からの舶来品の総称でしたが能装束では主に女性役のシテが着る表着として名が定着しております。
能装束には大きく分類して女性文様と男性文様とがあり、それは和様の文様は女性的、唐様は男性的とも言い換えることもできます。
女性は往々にして日本の色彩豊かな四季を反映した草花文様が多く優しく華麗に表現されることに対し、男性は格式高い蜀江文様や輪宝、瑞雲、雲版、丸龍、獅子、鳳凰など力強く霊的かつ荘厳に表現された文様が特徴です。
また能装束の配色は舞台装置としての効果を考慮したものであり、暖色と寒色を合わせるなど思い切りの良い配色の妙が見受けられるのが特徴です。
男性役の能装束「厚板」は唐織の彩度に比べるとグッと抑えられ落ち着きがありますが、ここにもやはり配色で魅せる試みがわかります。さらに「段替り」と呼ばれる技法により異なる地色や文様が表現された意匠は見所のひとつと言えるでしょう。
見つけた布や骨董品は、洗濯や磨く等せずにそのままにしてください。
基本的には綺麗な状態の方が骨董品の買取価格は高くなりますが、知識もなく磨く事は得策ではありません。
古い状態の物は弱いものが多く、逆に傷がつき価値が下がる可能性があります。
まずは拝見させていただき、価値のあるものでしたら買取させていただきます。
まずは、WEB査定にてお写真をお送りください。
お品物にもよりますが、買取できる場合もございます。
ただ、保存状態のよいお品物に比べると査定額は低下してしまいます。
ただし、価値が完全に無くなってしまうわけではございませんので、まずは一度ご相談下さい。
ただし、破損状況などによっては買取できかねない場合もございます。
お品によっては1点でも出張買取いたします。
まずは、お電話またはWEB査定より品物の詳細を教えてください。
ご不安があるようでしたら、WEB査定にて一度品物のお写真をお送りください。
出張料・査定料は無料です。
買取りにいたらなかった場合でも、費用などは一切いただきません。
その場で買取金額にご納得いただきましたら、即金にて買取させていただきます。
ご納得いただけなければ無理に買取りすることはありませんのでご安心してご利用ください。
いずれか1つご用意ください
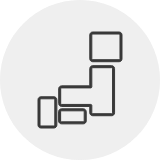
日本全国無料で
出張査定・買取行います。
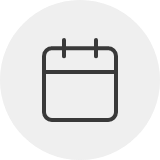
土日も対応可能。
日程調整してお伺い致します。

お値段にご納得頂ければ
その場で現金買取致します。
関東一円を中心に、全国無料で出張買取いたします。
関東の方はすぐにお伺い致します。