江戸期刺繍
関東一円を中心に、全国無料で出張買取いたします。
関東の方はすぐにお伺い致します。

東京美術倶楽部(桃李会 集芳会 桃椀会)所属
確かな鑑定力と豊富な販売ルートで
大切なお品物を少しでも高く買い取ります
出張・宅配・WEB
買取対応エリア
買取り1週間以内
キャンセル
東京美術倶楽部(桃李会 集芳会 桃椀会)所属
日本の伝統的染織品である着物や帯には、これまでに数多くの人間国宝に指定された方々、重要無形文化財に指定された産地織物が存在します。それは日本の長い歴史の中で育まれ洗練されてきた意匠であり、研ぎ澄まされた技法の証左でもあります。
今求められているのは世界で唯一無二の一点もの、極上の和様美です。そしてそれは失われた日本の美意識の再興・再発見でもあります。
室町時代に栄華を極めた技法「辻が花」を再興しようと試みた人間国宝・久保田一竹、民藝運動(民芸運動)の祖・柳宗悦に共鳴した母より染織を、富本健吉より芸術論を学びそれまで農村の手作業だった紬織を芸術の域まで高めたとさえ言われた人間国宝・志村ふくみ、沖縄が誇る伝統的染織品・芭蕉布の復興に尽くした人間国宝・平良敏子…先人達の残した遺産とも言うべき優れた染織品や着物を後世に伝えていくことが私たち着物に携わる者の使命であると確信しております。
高級着物をお売りの際に重要なのことは「作家性(織元・染元)」「産地染織」「証紙」「コンディション」です。
作家ものにも作家本人の作品であるものと工房で制作されたものがあり、この二つでは大きく評価がわかれます。また手織か織機でも評価が変わります。
西陣織の龍村美術織物と聞いて頭に浮かぶのが「龍村平蔵製」と「たつむら製」です。「龍村平蔵製」は龍村錦帯ともいい、初代龍村平蔵から当代4代目にわたり高島屋と制作してきた高島屋オリジナルの帯です。一方「たつむら製」は龍村美術織物の独自ブランドになります。漢字で「龍村製」と書かれた帯もございます。
例えば、ご家族の方が残された帯に「たつむら製」とあっても、あまりお着物に馴染みのない方ですとそれが手織が織機によるものか判別するのは難しいかもしれません。
産地染織は文字通り特定の産地の染織品なのですが、その産地の技法が重要無形文化財や伝統工芸品に指定されていることがございます。久留米絣は1956年という戦後の比較的早い段階で重要無形文化財の指定を受け、その後1976年には伝統工芸品の認定もされております。この久留米絣の技術保持者の代表作家が松枝玉記です。久留米絣の伝統的な手織による柄つくりと藍染を最も得意とし、短歌の才もあったことから、詩的感性を取り入れた文様や濃淡豊かに表現された藍染で唯一無二の作品を作り出すとともに久留米絣の発展に努めました。
それら「作家性(織元・染元)」や「産地染織」を担保するのが「証紙」です。証紙とは布地の織元や織物工業組合などが発行している紙で、織元の名前や正絹シール、伝統工芸品マークなどがあり、この証紙の有無が査定価格を大きく左右すると言っても過言ではございません。
もちろん証紙のない場合でも高級着物の買取り自体は可能で、鑑定力のある業者なら判別はつきます。しかしながら次の方にお渡しするということになりますと、ご購入されるお客様の立場からしますとやはり証紙があった方が安心材料となりますので結果的に買取価格が下がってしまう傾向にあります。
最後に「コンディション」です。着物は湿気に大変弱く、タンスなどにしまったままですとシミや虫食いの原因となり、結果的に査定額を下げてしまいます。
特に高級着物や作家ものですと一点もののお着物が存在します。定期的にお着物の状態を確認される上でも年に二回くらいの虫干しをお勧めいたします。
時期的には1月から2月の湿気の最も少ない時期と夏と秋についてしまった虫を払う意味でも10月から11月が最適かと存じます。
私たち呂芸は杉並区で1985年来、古布やお着物を中心に続けて参りました。その中で高級着物や特選着物などの鑑定眼を養い、ご依頼を受けた作家もののお着物など一点一点お客様に寄り添った査定を常に心がけております。
高級着物と言えども市場の需要や流行などもございます、そのような多角的要素なども鑑みるとともにこれまでの経験を活かし、高級着物を買取という形で次のお客様への橋渡しのお手伝いをさせていただいております。お客様がこれまで大切になさってきたお着物です、ご売却の折には経験と見識のある呂芸に是非お任せ下さいませ。
見つけた布や骨董品は、洗濯や磨く等せずにそのままにしてください。
基本的には綺麗な状態の方が骨董品の買取価格は高くなりますが、知識もなく磨く事は得策ではありません。
古い状態の物は弱いものが多く、逆に傷がつき価値が下がる可能性があります。
まずは拝見させていただき、価値のあるものでしたら買取させていただきます。
まずは、WEB査定にてお写真をお送りください。
お品物にもよりますが、買取できる場合もございます。
ただ、保存状態のよいお品物に比べると査定額は低下してしまいます。
ただし、価値が完全に無くなってしまうわけではございませんので、まずは一度ご相談下さい。
ただし、破損状況などによっては買取できかねない場合もございます。
お品によっては1点でも出張買取いたします。
まずは、お電話またはWEB査定より品物の詳細を教えてください。
ご不安があるようでしたら、WEB査定にて一度品物のお写真をお送りください。
出張料・査定料は無料です。
買取りにいたらなかった場合でも、費用などは一切いただきません。
その場で買取金額にご納得いただきましたら、即金にて買取させていただきます。
ご納得いただけなければ無理に買取りすることはありませんのでご安心してご利用ください。
いずれか1つご用意ください
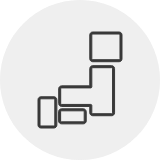
日本全国無料で
出張査定・買取行います。
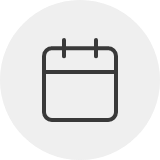
土日も対応可能。
日程調整してお伺い致します。

お値段にご納得頂ければ
その場で現金買取致します。
関東一円を中心に、全国無料で出張買取いたします。
関東の方はすぐにお伺い致します。