江戸期刺繍
関東一円を中心に、全国無料で出張買取いたします。
関東の方はすぐにお伺い致します。

東京美術倶楽部(桃李会 集芳会 桃椀会)所属
確かな鑑定力と豊富な販売ルートで
大切なお品物を少しでも高く買い取ります
出張・宅配・WEB
買取対応エリア
買取り1週間以内
キャンセル
東京美術倶楽部(桃李会 集芳会 桃椀会)所属
古布とは織・染・繍の織りなす美術品です。
素材も絹・麻・木綿や人絹(レーヨン) モスリン、そして靭皮繊維と呼ばれる樹木の皮や幹から採られた繊維など様々です。
それは人々の営みから生まれたものであり、土着性が強く影響される各地固有の文化 遺産に他なりません。 古布はアンティークの部類に入りますのでおよそ100年以上前の布帛を指します。昭和 戦前までと思っていただくとわかりやすいかと思います。古布は布という特性上、保存 状態、コンディションの良いものが時代が経てば経つほど少なくなりやすく、希少性が 高まる骨董品です。
また古布は茶道や民藝(民芸)など他の美術骨董品・鑑賞陶磁器、能や歌舞伎など日本の伝統芸能と密接な関係でもあります。例えるならば絵画における額のような存在でしょうか。
茶道ほど古布と密な関係の日本文化はないでしょう。茶道具を包む袋状の布を仕覆といい、茶席において茶入や茶杓とともに客の拝見に供されるものです。
点前に茶器を拭いたり、拝見する際に茶器の下に敷いたりして用いられる布を帛紗と言います。 時代のある、由来のある茶道具の仕覆には名物裂と呼ばれる、主に室町時代を中心に、鎌倉時代 から江戸時代中期あたりにかけ日本に渡ってきた古布が用いられます。
中国の宗・元・明・清より渡ってきた金襴・緞子・錦などや間道・風通・繻珍(しちん)・ 天鵞絨(びろうど)・印金(いんきん)・莫臥爾(もうる・モール)・更紗など南蛮貿易により渡ってきたものなどが挙げられます。名物裂の名前の由来は所蔵していた大名や茶人、また裂の文様、生産地や能装束として用いられる演目など様々です。
例えば小堀遠州です。小堀遠州は江戸初期の大名茶人の一人で、遠州流茶道の祖としてしられております。現在茶道の流派には表千家・裏千家・武者小路千家などございますが、その中でも遠州流・石州流・上田宗箇 流は武家茶道として伝えられております。
小堀遠州は裂の造詣も深く当時オランダやイギリスとの交易で渡ってきた更紗(日本古渡更紗)を武家文化に取り入れた第一人者でもあります。その遠州が裂を仕覆に用いたことは必然と言えます。
遠州の銘が打たれた名物裂に「遠州緞子(遠州七宝)」と呼ばれるものがあります。これが利休・織部・石州と経て武家の宗匠となった遠州が好んで使用した文様とされ名物裂として現在にも伝わっております。ディフォルメ化された菊・牡丹・椿を七宝文様と合わせ、それらを石畳文様の中に規則的に配列した構成からも遠州の現代に通ずる美的センスを感じさせます。
このように茶道における古布の役割は非常に重要なポイントです。大切な茶道具を包むのが仕覆・帛紗です。そこには持ち主様の思い入れがあります。 こだわりとも言っていいでしょう。
ですがそれは茶道具だけにとどまりません。
なぜなら古布というものは想いを包むものだからです。
古い布や着物はどうしても箪笥の肥やしになりやすく、いざ処分されようと思ったら量があり大変手間のかかるものに見えるかもしれません。
また布という特性上、一度袖を通したもの、あまり高いものに見えず、ボロキレのような古い布や着物だとなおさらだと思います。
だったらいっそ自治体の古布回収やリサイクル業者にお任せしてしまおう… そう思われる方も少なくないかと思います。
ですがその中に価値のある古布やお着物が眠っている可能性は十分にあります。布のはぎれ(ハギレ)や裂も同様です。
和服リメイクや市松人形の衣裳作り、ちりめん細工(縮緬細工) などされていた方の場合、お持ちの古布は江戸ちりめん(江戸縮緬)でしたり時代のある藍染の場合が多く見られます。
さらに古布や着物は先ほど申し上げたように持ち主様の想いがこもったものです。できる限り、価値のわかる方にお譲りしたいはずです。
その価値を見極め、更に次の代への橋渡しをする、それが古布を扱う者としての務め、礼儀だと私どもは考えております。
古布・着物買取作家一覧
【加賀友禅 】
木村雨山・談議所栄二・能川光陽・由水十久
【京友禅 】
田畑喜八・品川恭子・松井青々・吉野一廉
【友禅 】
中村勝馬・中村光哉・羽田登喜男・上野為二・田島比呂子・羽田登・山田貢・田島比呂子・森口邦彦・ニ塚長生
【江戸小紋】
小宮康孝・小宮康助・中村勇二郎・中島秀吉
【その他人間国宝】
江里佐代子・喜多川平朗・北村武資・甲田栄佑・五嶋敏太郎・児玉博・志村ふくみ・芹沢銈介・鎌倉芳太郎・玉那覇有公・南部芳松・平良敏子・宗廣力三・森口華弘・森山虎雄・吉田文之・六谷紀久男・福田喜重・鈴木慈人
浦野理一・久保田一竹・由水十久
【買取対象工房など】
尾峨佐染繍・大彦・川島織物・銀座きしや・久保耕・窪田織物・誉田屋源兵衛・翠山工房・ しょうざん(生紬)・白山工房・染めの北川・龍村美術織物・千總・都喜ヱ門・に志田 むら田・紋屋井関・山口美術織物・吉沢織物・ゑり善
見つけた布や骨董品は、洗濯や磨く等せずにそのままにしてください。
基本的には綺麗な状態の方が骨董品の買取価格は高くなりますが、知識もなく磨く事は得策ではありません。
古い状態の物は弱いものが多く、逆に傷がつき価値が下がる可能性があります。
まずは拝見させていただき、価値のあるものでしたら買取させていただきます。
まずは、WEB査定にてお写真をお送りください。
お品物にもよりますが、買取できる場合もございます。
ただ、保存状態のよいお品物に比べると査定額は低下してしまいます。
ただし、価値が完全に無くなってしまうわけではございませんので、まずは一度ご相談下さい。
ただし、破損状況などによっては買取できかねない場合もございます。
お品によっては1点でも出張買取いたします。
まずは、お電話またはWEB査定より品物の詳細を教えてください。
ご不安があるようでしたら、WEB査定にて一度品物のお写真をお送りください。
出張料・査定料は無料です。
買取りにいたらなかった場合でも、費用などは一切いただきません。
その場で買取金額にご納得いただきましたら、即金にて買取させていただきます。
ご納得いただけなければ無理に買取りすることはありませんのでご安心してご利用ください。
いずれか1つご用意ください
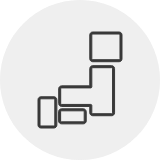
日本全国無料で
出張査定・買取行います。
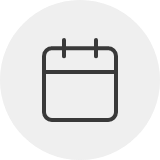
土日も対応可能。
日程調整してお伺い致します。

お値段にご納得頂ければ
その場で現金買取致します。
関東一円を中心に、全国無料で出張買取いたします。
関東の方はすぐにお伺い致します。